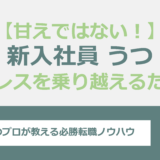「研修の内容が難しくて、全くついていけない…」
「周りの同期はできているのに、自分だけ仕事が覚えられない…」
「もう会社を辞めたい…」
入社して数ヶ月、新しい環境への期待と同時に、このような深刻な悩みを抱えていませんか。慣れない環境で成果を求められるプレッシャーと、理想と現実のギャップに、心が折れそうになっているかもしれません。
この記事を読めば、あなたが「ついていけない」と感じる根本的な原因が明確になり、明日からすぐに実践できる具体的な解決策が手に入ります。一人で抱え込み、何も対策をせずにいると、貴重な成長の機会を逃し、最悪の場合、早期離職という後悔の残る決断に至ってしまう可能性もあります。
本記事では、新入社員本人が取るべき対処法だけでなく、企業の人事・研修担当者向けに、新入社員を孤立させないための育成体制についても詳しく解説します。この壁を乗り越え、あなたが社会人として大きく成長するための第一歩を、ここから踏み出しましょう。
新入社員の約3割が「辞めたい」と感じている現実
まず結論からお伝えすると、あなたが「ついていけない」と感じていたとしても、それは決して特別なことではありません。多くの新入社員が、あなたと同じように悩み、壁にぶつかっています。
この事実は、客観的なデータにも表れています。株式会社マイナビが発表した「新入社員の意識調査(2025)」によると、入社後わずか2ヶ月の時点で、約3割の新入社員が「辞めたい」と思ったことがあると回答しているのです 。
さらに深刻なデータもあります。厚生労働省の調査によれば、大学を卒業して就職した新入社員のうち、3年以内に離職する人の割合は34.9%にものぼります。これは、新入社員の約3人に1人が、何らかの理由で会社を去っているという衝撃的な現実を示しています。
| 調査項目 | 結果 |
| 入社2ヶ月時点で「辞めたい」と思ったことがある人の割合 | 約30% |
| 大学卒業後3年以内の離職率 | 34.9% |
| 入社後にギャップを感じた人の割合 | 約45% |
これらのデータが示すように、「ついていけない」という感情は、あなた一人だけが抱える特殊な悩みではないのです。むしろ、多くの新入社員が通る道であり、成長の過程で誰もが経験しうる「当たり前」の感情と言えます。
大切なのは、その感情から目を背けず、原因を正しく理解し、適切な対処法を実践することです。この最初の壁を乗り越えることができれば、あなたは社会人として大きく飛躍できるはずです。
新入社員が「ついていけない」と感じる理由とは
では、なぜ多くの新入社員が「ついていけない」と感じてしまうのでしょうか。その原因は一つではなく、複数の要因が複雑に絡み合っています。ここでは、代表的な3つの理由を深掘りしていきます。
仕事の覚えが悪いと感じる
「何度も同じことを聞いている気がする」「メモを取っているのに、いざ実践となると頭が真っ白になる」。このように、仕事の覚えが悪いと感じてしまうのは、新入社員が最初にぶつかる大きな壁です。
これはあなたの能力が低いからではありません。現代の職場では、覚えるべき業務フロー、システム操作、社内ルールなどが膨大に存在します。個人の学習スピードには差があるにもかかわらず、研修は一律のペースで進むため、少しでもつまずくと、あっという間に取り残されたような感覚に陥ってしまうのです。
例えば、営業職であれば自社の商品知識、顧客情報、提案書の作成方法など、覚えるべきことは山積みです。これらを短期間でインプットし、すぐにアウトプットすることを求められるため、情報処理が追いつかなくなるのは当然と言えます。
事務職でも同様です。会計システムの操作、各種申請書類の作成ルール、社内の承認フローなど、初めて触れる業務が次々と押し寄せます。さらに、先輩社員は「これは常識」と考えて説明を省略することもあり、新入社員が理解できないまま業務が進んでしまうケースも少なくありません。
研修内容が難しすぎる
特にIT・プログラミング研修や専門知識を要する研修では、「内容が高度すぎて全く理解できない」という声が多く聞かれます。これは、新入社員の前提スキルや知識レベルに大きなばらつきがあるにもかかわらず、研修が一定のレベルを前提に進められることが原因です 。
例えば、プログラミング未経験の文系出身者と、学生時代からコーディング経験のある情報系学部出身者が、同じクラスで研修を受けるケースを考えてみてください。研修が後者のレベルに合わせて進められれば、前者がついていけなくなるのは当然です。
座学中心で実践の機会が少ない場合、学んだ知識がどう業務に活かされるのかイメージできず、学習意欲の低下にもつながります。「なぜこれを学ぶのか」「実際の業務でどう使うのか」という文脈が欠けていると、知識は単なる暗記事項となり、定着しにくくなるのです。
また、研修のスピードが速すぎることも問題です。1日に詰め込まれる情報量が多すぎると、復習する時間もないまま次の内容に進んでしまい、理解が追いつかないまま研修が終了してしまいます。
質問しづらい環境と孤立感
「こんな基本的なことを聞いて、呆れられないだろうか」「他の同期は理解しているのに、自分だけがわからないのでは」。このような不安から、質問をためらってしまう新入社員は少なくありません。
特に、大人数の講義形式の研修や、先輩社員が常に忙しそうにしている職場では、質問の心理的なハードルはさらに高くなります。誰にも相談できず、一人で悩みや不安を抱え込むことで孤立感が深まり、「自分だけが取り残されている」という感覚を強めてしまうのです。
このような心理的安全性が確保されていない環境は、学習効果を著しく阻害する大きな要因となります 。質問できない環境では、わからないことがわからないまま積み重なり、やがて業務全体についていけなくなってしまいます。
また、リモートワークが増えた現代では、対面でのコミュニケーション機会が減り、孤立感がさらに深まりやすい傾向にあります。オンライン研修では、他の参加者の反応が見えにくく、「自分だけがわかっていないのでは」という不安を抱きやすくなるのです。
「ついていけない」と感じた時の対処法
「ついていけない」という感情は、あなたが成長しようと真剣に仕事に向き合っている証拠です。ここでは、その壁を乗り越え、成長の糧に変えるための具体的な3つの対処法を紹介します。
メモを取ることを習慣化する
「メモを取っているのに覚えられない」という方は、メモの取り方を見直しましょう。重要なのは、後から見返して理解できること、そして必要な情報をすぐに見つけ出せることです。
効果的なメモの取り方として、5W2Hを意識する方法があります。「いつ(When)」「どこで(Where)」「誰が(Who)」「何を(What)」「なぜ(Why)」「どのように(How)」「いくらで(How much)」を明確にすることで、指示の抜け漏れを防ぎます。
例えば、上司から「来週の会議資料を作成しておいて」と指示された場合、以下のようにメモします。
- いつ: 来週月曜日の午前10時の会議で使用
- 何を: 第2四半期の営業成績報告資料
- どのように: PowerPoint形式、前回のフォーマットを使用
- 誰が: 営業部全員(約20名)が参加
- なぜ: 四半期ごとの定例報告のため
このように具体的にメモすることで、後から見返した時にも正確に再現できます。
さらに、自分専用のマニュアルを作成することも効果的です。教わった業務手順や操作方法を、スクリーンショットなどを活用して自分だけのマニュアルとしてまとめましょう。一度作成すれば、何度も同じことを聞く必要がなくなります。
デジタルツールの活用もおすすめです。OneNoteやEvernoteなどのノートアプリを使えば、キーワードで瞬時に情報を検索できます。手書きのメモと併用し、情報を一元管理することで、必要な情報にすぐにアクセスできるようになります。
上司や先輩に相談する
「ついていけない」という悩みは、一人で抱え込まず、勇気を出して上司や先輩に相談してみましょう。あなたの状況を客観的に見て、的確なアドバイスをくれるはずです。
まずは、相談しやすい人を見つけることから始めましょう。年齢の近い先輩や、普段から気にかけてくれる上司など、あなたが話しやすいと感じる相手に相談してみてください。必ずしも直属の上司である必要はありません。
相談する際は、具体的に伝えることが重要です。「ついていけません」と漠然と伝えるのではなく、「〇〇という業務の、△△の部分が理解できず、困っています」と具体的に伝えることで、相手も的確なアドバイスがしやすくなります。
例えば、「Excelのピボットテーブルの作り方がわからず、データ集計に時間がかかってしまっています。基本的な操作方法を教えていただけないでしょうか」というように、何に困っているのかを明確にします。
また、相談に乗ってもらった後は、感謝の気持ちを伝えることを忘れずに。「お時間いただき、ありがとうございました。おかげで解決しました」と伝えることで、次回も相談しやすい関係性が築けます。
定期的に設けられている1on1ミーティングも、相談の絶好の機会です。日々の業務で聞きづらいことをまとめて質問したり、キャリアの悩みを相談したりできます。
自分のペースで学習する
業務時間内にすべてを理解・習得するのは困難です。終業後や週末に、自分のペースで復習する時間を作りましょう。
会社でeラーニングが導入されている場合は、積極的に活用してください。自分の理解度に合わせて何度も繰り返し学習でき、通勤時間などのスキマ時間にも学べます。
業務に関連する書籍やオンライン講座で補強するのも効果的です。例えば、営業職であれば営業スキルに関する書籍、エンジニアであればプログラミングのオンライン講座など、体系的な知識をインプットできます。
重要なのは、アウトプットを意識することです。学んだことを自分の言葉で説明してみたり、簡単な資料にまとめてみたりすることで、知識の定着度が格段に上がります。同期に教えるつもりで説明してみるのも良い方法です。
ただし、無理は禁物です。毎日深夜まで勉強するような生活を続けると、心身が疲弊してしまいます。週に2〜3回、1時間程度の復習時間を確保するなど、無理のない範囲で継続することが大切です。
企業側が取るべき対策
新入社員が「ついていけない」と感じる問題は、個人の能力や意欲だけの問題ではありません。むしろ、受け入れる企業側の環境や育成体制に起因するケースが非常に多いのです。ここでは、新入社員の早期離職を防ぎ、全員を戦力化するために企業が取るべき3つの対策を解説します。
段階的な学習プログラムの構築
画一的な研修プログラムでは、必ず「ついていけない」社員が出てきます。重要なのは、新入社員一人ひとりのスキルレベルや学習ペースを考慮した、段階的な学習プログラムを構築することです。
まず、事前アセスメントを実施しましょう。入社前にスキルチェックや適性検査を行い、個々の基礎スキルや特性を把握します。例えば、ITスキル、ビジネスマナー、コミュニケーション能力などを測定し、新入社員のレベルを可視化します。
アセスメントの結果に基づき、基礎補強プログラムを提供します。ITスキルが不足している新入社員には、基礎的なPC操作やOfficeソフトの使い方を学ぶ機会を設けます。ビジネスマナーに不安がある新入社員には、電話応対や名刺交換などの基礎研修を追加します。
研修全体の難易度を段階的に設定することも重要です。「基礎→応用→実践」と段階的に難易度を上げていくことで、全員が無理なくステップアップできる環境を整えます。各段階で理解度チェックを行い、理解が不十分な場合は次のステップに進む前に補講を実施します。
チーム学習による相互サポート体制
一人で学習する環境は、孤立感や不安を増大させます。チームでの学習や、先輩社員によるサポート体制を構築することで、質問しやすく、互いに助け合える文化を醸成します。
チーム学習を導入しましょう。4〜5名の小グループで学習を進めることで、メンバー同士が教え合い、質問しやすい環境が生まれます。グループ内で役割分担を行い、各自が調べた内容を共有することで、学習効率も高まります。
メンター制度の導入も効果的です。年齢の近い先輩社員をメンターとして任命し、業務の指導だけでなく、精神的なサポートも行います。メンターには、定期的な1on1の実施を義務付け、新入社員の悩みや不安を早期にキャッチアップできる体制を整えます。
メンターは、新入社員にとって「何でも聞ける存在」となることが重要です。業務の質問だけでなく、「こんなことを聞いても良いのか」という不安や、「上司に相談しづらいこと」なども気軽に話せる関係性を築きます。
ピアラーニングも推奨しましょう。新入社員同士が学び合う文化を育むことで、「自分だけができない」という孤立感を解消できます。同期同士で勉強会を開催したり、お互いの課題を共有したりする機会を設けます。
心理的安全性の高い環境づくり
「こんなことを聞いたら怒られるかもしれない」という不安は、新入社員の成長を妨げる最大の要因です。どんな些細なことでも質問でき、失敗を恐れずに挑戦できる心理的安全性の高い環境を意図的に作り出す必要があります。
経営層や管理職が率先して、「質問は歓迎」というメッセージを繰り返し発信しましょう。研修の冒頭で「どんな質問でも歓迎します」「わからないことは恥ずかしいことではありません」と明言することで、新入社員の心理的なハードルを下げます。
失敗を許容する文化を醸成することも重要です。失敗を責めるのではなく、「良い挑戦だった」「次に活かそう」とポジティブにフィードバックする文化を育みます。失敗から学ぶことの価値を伝え、挑戦を評価する姿勢を示します。
1on1ミーティングを定期的に実施しましょう。上司と部下が1対1で対話する時間を週1回または隔週で設け、業務の進捗だけでなく、キャリアの悩みやプライベートの相談もできる関係性を構築します。
1on1では、上司が一方的に話すのではなく、新入社員の話を傾聴することが重要です。「最近困っていることはない?」「何か不安に感じていることはある?」と質問し、新入社員が本音を話しやすい雰囲気を作ります。
「ついていけない」は成長のチャンス
理論だけでなく、実際に困難を乗り越えた先輩たちの声は、あなたにとって大きな勇気となるはずです。ここでは、具体的な体験談を紹介します。
実際に乗り越えた人の体験談
IT未経験からエンジニアへ。「わからない」を強みに変えたAさん
「文系出身で、プログラミングは全くの未経験。IT研修が始まった途端、専門用語の嵐でパニックになりました。同期はどんどん先に進んでいくのに、自分だけが取り残されている感覚。毎日泣きながら通勤していました」
そう語るAさんは、「わからない」ことを徹底的に言語化することから始めました。「『何がわからないのか』を具体的に説明できるように、エラーメッセージを全て記録し、試したことをリストアップしました。そして、メンターの先輩に『ここまで試しましたが、このエラーが解決できません』と質問するようにしたのです」
その結果、質問の質が上がり、先輩からのアドバイスも的確になりました。今では、新人研修のチューターとして、後輩の「わからない」に寄り添う存在になっています。
同期との協力で営業成績トップに。チームで乗り越えたBさん
「営業部に配属されたものの、人見知りでうまく話せず、全く契約が取れませんでした。同期が次々と初契約を上げていく中で、自分だけが成果を出せず、毎日のように上司から叱責されていました」
Bさんは、同じように悩んでいた同期3人と自主的な勉強会を始めました。「お互いの商談の録音を聞き合ってフィードバックしたり、成功事例を共有したりしました。一人では心が折れそうでしたが、仲間がいたから頑張れたんです」
同期と協力してトークスキルを磨いた結果、Bさんは入社1年目の後半には部署でトップの営業成績を収めるまでに成長しました。
メンターのサポートで自信を取り戻したCさん
「配属された部署の先輩たちが皆忙しそうで、質問するタイミングが全く掴めませんでした。簡単なミスを繰り返しては落ち込む、という負のスパイラルに陥っていました」
Cさんの転機となったのは、メンター制度による週1回の1on1ミーティングでした。「メンターの先輩が、『どんな些細なことでも良いから、この時間は何でも聞いて』と言ってくれたんです。そこで初めて、自分が抱えている不安を全て打ち明けることができました」
メンターはCさんの話を傾聴し、具体的な改善策を一緒に考えてくれました。心理的な安全基地ができたことで、Cさんは徐々に自信を取り戻し、自ら積極的に業務に取り組めるようになりました。
よくある質問(FAQ)
最後に、新入社員が抱きがちな疑問について、Q&A形式でお答えします。
- 新入社員が一番辛い時期はいつですか?
- 一般的には、入社後3ヶ月〜半年が最も辛い時期と言われています。研修が終わり、OJTが始まって本格的な業務に携わる中で、理想と現実のギャップに直面しやすいためです。この時期を乗り越えれば、徐々に仕事に慣れ、精神的にも安定してきます。
- 何ヶ月くらいで仕事に慣れますか?
- 個人差や職種にもよりますが、多くの人が半年〜1年程度で一通りの業務に慣れると感じるようです。ただし、これはあくまで目安です。焦らず、自分のペースで着実にスキルを身につけていくことが大切です。
- 辞めたいと思うのは、甘えなのでしょうか?
- 決して甘えではありません。前述の通り、多くの新入社員が同じように「辞めたい」と感じています。重要なのは、その感情の背景にある原因を冷静に分析し、解決策を探ることです。この記事で紹介した対処法を試しても状況が改善しない場合は、異動や転職を検討するのも一つの選択肢です。
まとめ:あなたの「ついていけない」は、成長の伸びしろです
本記事では、新入社員が「ついていけない」と感じる3つの理由と、それを乗り越えるための3つの具体的な対処法、そして企業側が取るべき3つの対策について解説しました。
「ついていけない」と感じる3つの理由
- 仕事の覚えが悪いと感じる
- 研修内容が難しすぎる
- 質問しづらい環境と孤立感
乗り越えるための3つの対処法
- メモを取ることを習慣化する
- 上司や先輩に相談する
- 自分のペースで学習する
企業側が取るべき3つの対策
- 段階的な学習プログラムの構築
- チーム学習による相互サポート体制
- 心理的安全性の高い環境づくり
「ついていけない」という感情は、あなたが真剣に仕事に向き合っているからこそ生まれるものです。それは決して恥ずかしいことではなく、むしろ大きな成長のチャンスと捉えることができます。
一人で抱え込まず、この記事で紹介した対処法を一つでも試してみてください。そして、周りの上司、先輩、同期に勇気を出して相談してみてください。あなたの周りには、必ずサポートしてくれる人がいます。
もし、あなたが人事・研修担当者で、新入社員の育成方法にお悩みであれば、外部の専門家の力を借りるのも有効な手段です。効果的な研修プログラムの設計や、心理的安全性の高い組織づくりについて、プロの視点からアドバイスを受けることで、新入社員の定着率と成長速度を飛躍的に高めることができるでしょう。
あなたの社会人としてのキャリアは、まだ始まったばかりです。この壁を乗り越え、輝かしい未来を築いていくことを心から応援しています。
参考文献
株式会社マイナビ. (2025). 2025年卒新入社員意識調査レポート. https://service.alue.co.jp/report/fy25-new-employee-2025
厚生労働省. (2024). 新規学卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者). https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000177553_00007.html
OpenWork. (2025). 3年以内に辞めたZ世代の入社&退職理由ランキング. https://www.openwork.co.jp/press/2025022701
Google re:Work. 心理的安全性を高める. https://rework.withgoogle.com/jp/guides/understanding-team-effectiveness/
 転職マガジン
転職マガジン